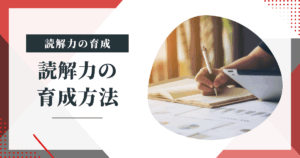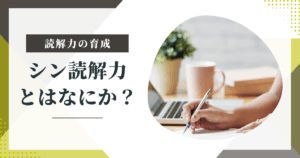【“わかっているフリ”の落とし穴】教科書が読めない子どもたちの実態とその原因とは?
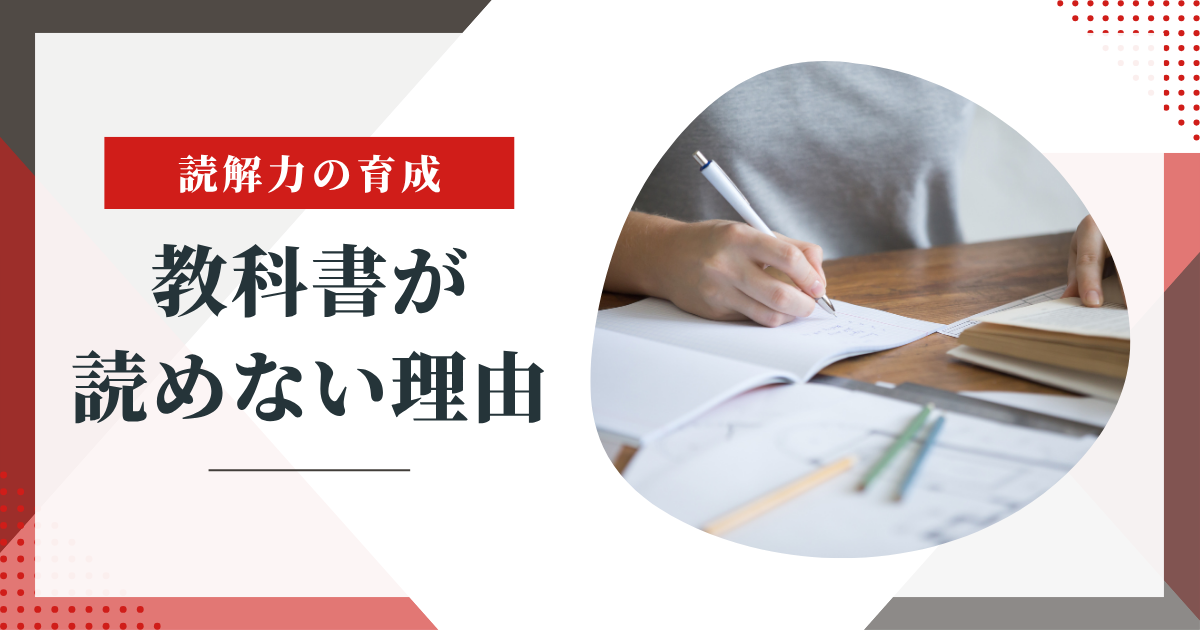
はじめに:本当に「読めている」のか?
授業中、先生の問いかけに「うん」とうなずく。家で音読をしていても、スラスラと読んでいるように見える。
「ちゃんと読めてるな」
そう思ってしまう保護者や先生は多いかもしれません。しかし、それは本当に“読めている”のでしょうか?
新井紀子氏が全国の子どもたちに行ったリーディングスキルテスト(RST)の結果から見えてきたのは、「見かけは読めているが、意味が理解できていない」子どもたちの存在でした。
今回は、「教科書が読めない」とは具体的にどういうことなのか。私が教育現場で出会った実例を交えながら、その実態と原因を深掘りしていきます。
事例1:「音読は得意。でも意味はつかめていない」
小学校4年生のAくんは、音読がとても上手でした。句読点の位置も意識し、抑揚もあり、読むスピードも申し分ありません。
しかし、「今読んだ内容を説明してみて」と聞くと、Aくんは黙り込みました。数分前に読んだばかりの教科書の内容が、頭の中に残っていなかったのです。
これは「音読=理解」ではないことを象徴する典型的な例です。文章を声に出して読むことと、その意味を論理的に把握することはまったく別のスキルなのです。
事例2:「“それ”が何を指しているのかわからない」
中学1年生のBさんは、国語の読解問題で高得点を取ることができませんでした。内容の理解はある程度できているように見えたのですが、「指示語」が苦手でした。
たとえば、「このことが原因で〜」という一文があったとき、「このこと」が何を指しているのかを尋ねると、本文中の全く違う箇所を答えてしまいます。
新井氏の研究でも明らかになっていますが、「照応解決(指示語の読み取り)」は、多くの子どもたちがつまずくポイントです。この力が不十分だと、文章のつながりを正しく理解できず、全体の意味を取り違えることになります。
事例3:「設問の意味を取り違えてしまう」
小学5年生のCくんは、算数の成績が思うように伸びず、家庭では「文章題になるとできない」と悩まれていました。
実際に問題文を読んでもらうと、「Aさんは1個120円のりんごを3個買いました。このときの合計金額は?」という問いに対し、「3÷120=40円」と解答。
計算ミスではなく、「問いの意味を正確に読めていなかった」のです。
文章問題が苦手な子の多くは、「質問されている内容」を正確に読み取る力が不足しています。これは国語だけの問題ではなく、読解力がすべての教科に影響を与えている証拠です。
なぜ子どもたちは「読めていない」のか?
こうした事例に共通するのは、子ども自身が「読めていないことに気づいていない」ことです。
● 原因1:教科書を“音”として捉えている 多くの子どもは、教科書を「音読するもの」「読むふりをするもの」として受け取っており、“意味を理解するためのツール”として扱っていません。
● 原因2:「わからない」と言い出しにくい空気 授業中に「ここがわからない」と言い出すのは、子どもにとっては非常に勇気のいることです。その結果、“わかったふり”が習慣化してしまい、本人すら読めていないことに気づかなくなるのです。
● 原因3:読解指導の不足 読解力を体系的に教える機会は、学校教育の中でも限定的です。「読書をすれば読解力は育つ」という誤解のもと、指導が放任されてしまっているケースもあります。
「読めていないこと」にどう気づかせるか?
最初のステップは、「自分が読めていないかもしれない」と子ども自身が気づくことです。そのためには:
- 読んだあとに「今の内容を説明してみて」と尋ねる
- 指示語の意味を都度確認させる
- 設問と本文を照らし合わせながら考えさせる
- 問いかけに対して“具体的な言葉”で答えさせる
こうした問いかけを通して、「読めているかどうかをチェックする姿勢」が少しずつ身についていきます。
まとめ:「読めていない」という現実から目を背けない
新井紀子氏の研究は、「日本の子どもたちは教科書を読めていない」という現実を突きつけました。しかしそれは、悲観すべきことではなく、“正しい対処”ができるための第一歩でもあります。
「読めていない子」を叱る必要はありません。ただし、「読めているつもり」を放置することは、学びの根を枯らすことになってしまいます。
まずは、子どもの読解力を信頼しすぎず、「意味をつかんでいるか?」を丁寧に確認することから始めてみてください。
次回は、AI時代に求められる“意味を読む力”とは何か、人間の学びの本質に踏み込んでいきます。